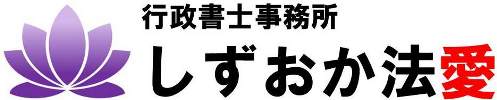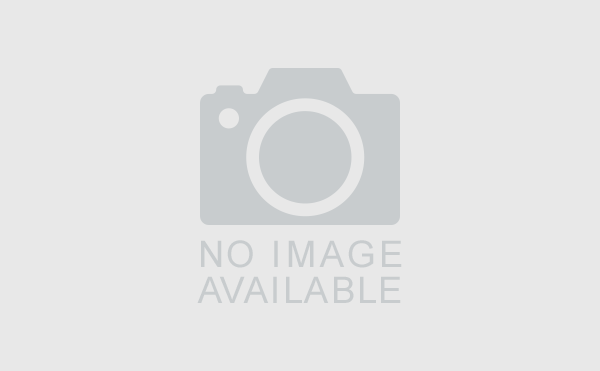【相続人必見】自筆証書遺言書保管制度を利用した場合の死後の手続きを徹底解説!
自筆証書遺言書保管制度をご存知ですか?これは、ご自身で作成した遺言書を法務局が保管してくれる制度で、令和2年7月10日から開始されました。この制度を利用していた故人の遺言書について、相続人の方が亡くなられた後にどのような手続きを行うべきか、詳しく解説します。
- まずは遺言書が保管されているかを確認!「遺言書保管事実証明書」の請求
故人が自筆証書遺言書を法務局に保管していたかどうかが不明な場合、まずは「遺言書保管事実証明書」を請求して確認することができます。
○誰が請求できる?
•相続人
•受遺者等(遺言書に記載された財産を受け取る人)
•遺言執行者等
•これらの者の親権者や成年後見人等の法定代理人
○どこで請求できる?
•全国どこの遺言書保管所でも可能です。
•郵送での請求もできます。
○必要な書類と手数料
•請求書: 法務省ホームページからダウンロードするか、法務局窓口で受け取ってください。
•遺言者の死亡の事実が確認できる戸籍または除籍謄本
•請求人の住民票の写し
•その他、請求人が相続人・法定代理人・法人の場合は別途書類が必要です。
•手数料: 1通につき800円(収入印紙で納めます)。
○手続きの流れ
STEP 1.請求先の確認: 全国どこの遺言書保管所でも可能です。
STEP 2.必要書類の準備: 上記の書類を揃えます。
STEP 3.交付請求の予約: 法務局手続き案内予約サービスの専用ホームページ、電話、または窓口で予約します。郵送でも請求可能です。
STEP 4.交付の請求: 請求書と添付書類を持参または郵送で提出します。郵送の場合は、返信用封筒と切手を同封してください。
STEP 5.証明書の受取: 窓口請求の場合は顔写真付き身分証明書を持参します。郵送請求の場合は住民票上の住所宛に送付されます。 - 遺言書の内容を確認・利用する!「遺言書情報証明書」の請求
遺言書が保管されていることが確認できたら、その内容を証明する「遺言書情報証明書」を取得することができます。この証明書は、家庭裁判所の検認手続きが不要で、相続登記や各種手続きに利用できるため大変便利です。
○誰が請求できる?
•法定相続人
•遺言書に記載された受遺者及び遺言執行者(「関係相続人等」)
•遺言者の死亡後に限ります。
•任意代理は認められていません。
○どこで請求できる?
•全国すべての遺言書保管所で可能です。
○必要な書類と手数料 :「関係遺言書保管通知」を受領しているかどうかで、必要書類が異なります。
●共通の必要書類
•遺言書情報証明書の交付請求書: 1通につき1,400円(収入印紙で納めます)。関係遺言書保管通知の添付があれば、請求書の一部の記載を省略できます。
•受取方法に応じた書類:
【窓口での受取】請求人の顔写真付き官公署発行の身分証明書(有効期限内のもの)
【郵便での受取】請求人の住所氏名を記載した返信用封筒(切手要)
•請求人が受遺者、遺言執行者、法人、法定代理人の場合は別途追加書類が必要です。
●「関係遺言書保管通知」をまだ受領していない場合
•法定相続情報一覧図の写し(法定相続人全員の住所記載あり/発行日から3か月以内のもの)が必要です。
•もし法定相続情報一覧図がない場合でも、以下の全てがあれば請求できます。
遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続人全員の戸籍謄本(発行日が遺言者死亡後のもの)
相続人全員の住民票(発行日から3か月以内のもの)
●「関係遺言書保管通知」をすでに受領している場合
•請求人の住民票
○手続きの流れ
STEP 1.請求先の確認: 全国どこの遺言書保管所でも可能です。
STEP 2.必要書類の準備: 上記の書類を揃えます。
STEP 3.交付請求の予約: 法務局手続き案内予約サービスの専用ホームページ、電話、または窓口で予約します。受付時間は平日8時30分から17時15分までです(土日祝日・年末年始は除く)。郵送での請求も可能です。
STEP 4.交付の請求: 請求書と添付書類を持参または郵送で提出します。
STEP 5.証明書の受取: 窓口請求の場合は顔写真付き身分証明書を持参します。郵送請求の場合は住民票上の住所宛に送付されます。
STEP 6.他の相続人等への通知: 相続人などが証明書の交付を受けると、遺言書保管官は、遺言書が法務局に保管されていることを他の相続人全員に通知します。 - 遺言書そのものの内容を閲覧する!「遺言書の閲覧」の請求
遺言書の内容を直接確認したい場合は、遺言書の閲覧を請求することができます。
○誰が請求できる?
•相続人
•受遺者等
•遺言執行者等
•これらの者の親権者や成年後見人等の法定代理人
○どこで閲覧できる?
•モニターによる閲覧: 全国どこの遺言書保管所でも可能です。
•遺言書原本の閲覧: 遺言書が保管された遺言書保管所のみとなります。
○必要な書類と手数料
•必要書類は「遺言書情報証明書」の請求とほぼ同様です(手数料を除く)。
•手数料:
モニターで閲覧する場合: 1回につき1,400円
原本の閲覧をする場合: 1回につき1,700円
=>いずれも収入印紙で納めます。
○手続きの流れ
STEP 1.閲覧先の確認: モニター閲覧は全国どこでも、原本閲覧は保管所のみ。
STEP 2.必要書類の準備: 上記の書類を揃えます。
STEP 3.閲覧の請求の予約: 予約が必要です。
STEP 4.閲覧の請求: 請求書と添付書類を持参します。
STEP 5.保管された遺言書の閲覧: 実際に閲覧します。
STEP 6.他の相続人等への通知: 相続人などが遺言書の閲覧をすると、遺言書保管官は、遺言書が法務局に保管されていることを他の相続人全員に通知します。
以上の手続きを行うことで、故人が残した自筆証書遺言書の内容を、相続人の方が適切に確認し、相続手続きを進めることができます。この制度をぜひご活用ください。より詳しい情報や最新の様式については、法務省のホームページもご参照ください。