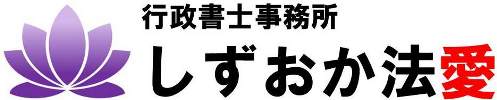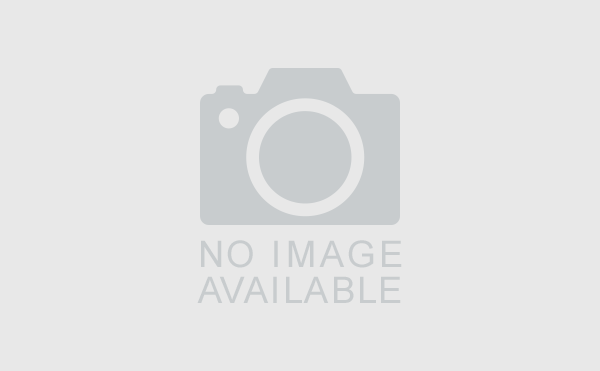不動産登記制度が変わる!所有者不明土地問題解消に向けた新ルールとは?
皆様は、「所有者不明土地」という言葉をご存知でしょうか? 相続登記がされなかったり、所有者の住所が変わっても登記が更新されなかったりすることで、登記簿を見ても所有者が分からない、あるいは分かっても連絡が取れない土地のことです。全国では九州本島に匹敵するほどの広大な土地が所有者不明となっているとも言われ、公共事業の阻害や土地利用の困難化、隣接する土地への悪影響など、深刻な社会問題となっています。
こうした問題の解消を目指し、令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立し、同年4月28日に公布されました。これらの法律は、所有者不明土地の発生予防と土地利用の円滑化の両面から、民事基本法制の総合的な見直しを行うものです。
今回はその中でも、特に「登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し」に焦点を当て、その概要を3つのポイントに分けてご紹介します。これらの見直しは、令和5年4月から段階的に施行されていますので、ぜひ最後までご覧ください。
1.相続登記・住所等の変更登記の申請義務化がスタート!
これまで任意だった不動産登記が、いよいよ義務化されます。これは、所有者不明土地の発生原因の約3分の2が相続登記の未了であることや、住所変更登記の未了も大きな原因となっているため、その発生を根本から予防しようとするものです。
1)相続登記の申請義務化
○ いつから? : 令和6年4月1日から施行されています。
○ どんな義務? : 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。もし遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記申請が必要です。
○ 違反すると? : 正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
○ 過去の相続も対象? : 令和6年4月1日より前に相続した不動産で、まだ相続登記がされていないものも義務の対象です。この場合は、令和9年3月31日までに相続登記の申請をしなければなりません。
○ 安心ポイント! : 登記官が義務違反を把握しても、すぐに過料が科されるわけではありません。まずは催告(申請を促す通知)が行われ、その催告に応じて変更登記をすれば、過料通知は行われません。
2)住所等の変更登記の申請義務化
○ いつから? : 令和8年4月1日から施行されます。
○ どんな義務? : 不動産の所有権の登記名義人に対し、住所などを変更した日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。
○ 違反すると? : 正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。施行日前の変更でも、まだ登記されていない場合は義務化の対象となります(猶予期間あり)。
○ 安心ポイント! : 相続登記と同様に、義務違反が把握されてもすぐに過料ではなく、まずは催告が行われ、それに応じて登記すれば過料通知は行われません。また、「正当な理由」として、重病やDV被害、経済的困窮などが例示されており、個別の事情も考慮されます。
2.手続きの簡素化・合理化で負担を軽減!
義務化に伴い、登記申請の負担を軽減するための仕組みも導入されます。
1)相続人申告登記
○ いつから? : 令和6年4月1日から施行されています。
○ どんな制度? : 相続人が多数で戸籍書類の収集に時間がかかるなど、すぐに相続登記の申請が難しい場合に、簡易に義務を履行できる仕組みです。特定の相続人が単独で、自らが登記簿上の所有者の相続人であることなどを3年以内に登記官に申し出れば、登記官がその氏名・住所等を登記に付記してくれます。
○ メリットは? : 単独で申し出が可能、押印や電子署名が不要、提出書類が少ない、非課税、といった点が挙げられます。
○ 注意点! : この登記は、不動産の権利関係を公示するものではないため、不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合には、別途、通常の相続登記の申請が必要です。
•
2)他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記
○ いつから? : 令和8年4月1日から施行されます。
○ どんな仕組み? : 登記名義人の負担軽減のため、登記官が他の公的機関(個人の場合は住民基本台帳ネットワークシステム、法人の場合は商業・法人登記システム)から取得した情報に基づき、職権で変更登記ができるようになります。
○ 個人の場合: 事前に「検索用情報」(氏名、振り仮名、住所、生年月日、メールアドレスなど)を法務局に提供しておくことで、法務局が定期的に住基ネットに照会し、住所等に変更があれば本人の了解を得て職権で変更登記を行います。DV被害者等、最新の住所を公示することに支障がある方もいるため、本人の了解が必須とされています。
→ 検索用情報の申出は令和7年4月21日から先行施行されます。
○ 法人の場合: 不動産登記簿に会社法人等番号が登記されていれば、商業・法人登記上で住所等に変更があった際に、不動産登記システムに通知され、職権で変更登記が行われます。
→ 会社法人等番号の申出は令和6年4月1日から先行施行されています。
3)法定相続情報証明制度の活用拡大
○ いつから? : 令和6年4月から適用されています。
○ どんな仕組み? : 相続人が戸籍関係書類と一緒に「法定相続情報一覧図」を法務局に提出し、その写しの認証を受ける制度です。これにより、相続登記だけでなく、銀行手続など他の相続手続でも戸籍謄本を何度も提出する必要がなくなります。
○ さらなる簡素化! : 相続登記の申請義務化に伴い、不動産登記手続きにおいて、法務局が各一覧図に付す固有の番号である「法定相続情報番号」を提供すれば、戸籍謄本や一覧図の写しの添付を省略することができるようになりました。
3.その他の見直し
上記の義務化や簡素化以外にも、所有者不明土地問題の解消に資する様々な見直しが行われています。
1)登記簿に記録する事項の追加
法人が不動産の所有者として登記される場合、その会社法人等番号が登記されます。
海外居住者が不動産の所有者として登記される場合、国内連絡先が登記されます。
これらは令和6年4月1日から施行されています。
2)旧姓(旧氏)・ローマ字氏名併記
希望すれば、氏名に旧姓(旧氏)を併記できるようになります。外国人の場合はローマ字氏名も併記されます。
こちらも令和6年4月1日から施行されています。
3)DV被害者等の保護のための特例
DV被害者等からの申し出により、登記事項証明書等には現住所に代えて、連絡が取れる「公示用の住所」を記載できるようになります。
これも令和6年4月1日から施行されています。
4)所有不動産記録証明制度の創設
令和8年2月2日から施行される制度です。
親が亡くなったが、どこに不動産を所有していたか分からない、といった場合に、登記官が特定の被相続人(亡くなった親など)が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧にして証明する制度です。これにより、不動産の把握が容易になります。
今回の法改正は、所有者不明土地問題の解消という喫緊の課題に対応するための重要な一歩です。義務化されたからといって焦る必要はありませんが、制度を理解し、準備を進めることが大切です。
もし、ご自身の不動産に関する登記について不安や疑問があれば、お近くの法務局や、日本司法支援センター(法テラス)、あるいは弁護士、司法書士、土地家屋調査士などの専門家 に相談することを強くお勧めします。法務局では「登記手続案内」という予約制の相談サービスも提供していますので、ぜひ活用してみてください。
所有者不明土地をなくし、より円滑な土地利用ができる社会を目指して、私たち一人ひとりが不動産登記の重要性を再認識する機会となるでしょう。